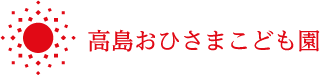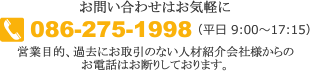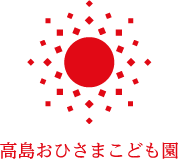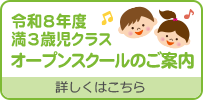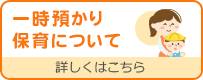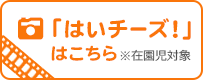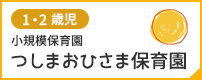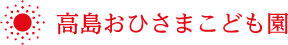株式会社アイギス 脇貴志先生による危機管理研修がありました。
重大事故検証報告書の事故事例をもとにお話を聞いたり、グループワークをしたりしました。
保育の中で「あれは大丈夫かな」「ちょっと心配だな」と危険に気付くこと、また、それを職員間で言い合える関係性が大切だと学びました。
子どもの動きを想像し、職員で連携を取り、今まで以上に危険がないか見守っていかなければならないと感じました。
子どもたちが安全に遊ぶことができるよう、自分の保育を振り返り、行動と考えを改めていきたいと思います。
高島おひさまこども園 塩見 記