私たち保育教諭は、発達援助、生活援助、保護者の方に対する相談や助言に関する、知識や技術などを生かして、支援を行う必要があると学びました。
また、児童虐待を防ぐために、早期の発見や対応を意識した支援も大切に保育を行っていきたいと思います。
高島おひさまこども園 宇和佐 芽 記
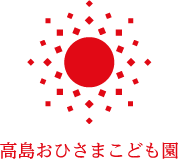

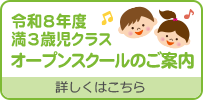

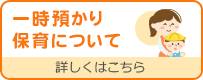

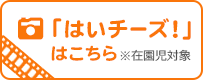 交通アクセス
交通アクセス

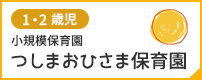
私たち保育教諭は、発達援助、生活援助、保護者の方に対する相談や助言に関する、知識や技術などを生かして、支援を行う必要があると学びました。
また、児童虐待を防ぐために、早期の発見や対応を意識した支援も大切に保育を行っていきたいと思います。
高島おひさまこども園 宇和佐 芽 記
この研修を通して、『育みたい資質・能力』は、前日にできなかったことを、今日どうすればできるようになるかを、繰り返し試す活動によって育まれるため、保育教諭は、子どもがこのような活動を経験できるように援助をするべきと学びました。
遊びにおいては、一人で遊ぶことも、集団で遊ぶことも、発達過程の一部であります。そのために私たち保育教諭はそれぞれの子どもの興味に合わせた環境構成をする必要があり、個々の子どもの発達に応じた保育内容を考えていきたいと思います。
高島おひさまこども園 宇和佐 芽 記
この研修を通して、子どものアレルギー事故の予防対策には、全職員を含めた関係者全員が共通理解をすること、職員間が連携をとり、組織的に対応をすることが重要だと改めて学びました。
そして、園の給食は毎日あるので、子どもたちにとって食事の時間が楽しいと感じられるような環境づくりを工夫していきたいと思います。
高島おひさまこども園 宇和佐 芽 記
保護者の方に対して
1.非審判的態度で臨む
2.非言語的メッセージも観察
3.すべてを肯定的に受け止めながら十分に聴く
4.繰り返される訴えがあった場合はその内容を整理し受け止める
という4つのことが大切で、心に留めて対応をしていきたいと思った。
高島おひさまこども園 塩見 ゆりあ 記
今回の研修を通して、感染症の予防には、施設内・職員の衛生管理が重要であることを改めて感じました。
衣服、寝具、哺乳瓶、おもちゃなどは、洗濯や(熱湯)消毒等を丁寧に行い清潔に保つことが大切であると再認識しました。
職員自身が感染しないように、使い捨て手袋を活用するなど、日々徹底していきたいと思います。
高島おひさまこども園 塩見 ゆりあ 記
『保健衛生・安全対策』の研修で、様々な配慮点を学ぶことができた。
重大事故が発生しやすい場面としては、睡眠中・プール水遊び・誤嚥・食物アレルギーなどであることを再確認した。
睡眠中の配慮点としては、うつぶせ寝を勧められている子ども以外は、仰向けに寝かせること、子どもの顔が見えるようにすること、紐状のものを近くに置かない等である。
プール遊びは、監視者は監視に専念すること等。
食物アレルギーに関しては、アレルギー児の食事の区別が見て分かるように工夫をすることが必要である。
高島おひさまこども園 久山 知華 記
今回の研修で、保育士の相談援助スキルの必要性、そして支援者としての態度の重要性を再確認した。
保護者の方のあるがままを受け入れて援助すること、行動や思考に対して善悪の評価をせずに援助をすることなど、保育士として働く上でとても大切なことを学ぶことができた。
高島おひさまこども園 久山 知華 記
障害児保育では、
以上の構造化4つの視点から支援方法を学ぶことができた。
視覚的手掛かりをもとに、その子のための支援、環境を整えるなど、障害児保育においての基礎を改めて学び、再確認する良い機会となった。
高島おひさまこども園 久山 知華 記
子どもたちが「何に興味関心があるのか。」そして、保育者自身のやりたいことを行うのではなく、それを通して子どもたちに「何を学ばせたいのか。何を育てたいのか。」を明確に、“環境作り”を行っていくことが大切であると学びました。保育者自身の押し付けにならないように気をつけていきたいです。
この研修を通して、『幼児教育』が担う役割を心に留め、日々の保育を丁寧に行うことが大変重要であると改めて再確認しました。
高島おひさまこども園 久山 知華 記
保育教諭は、それぞれの子どもの興味に合わせた環境構成をする必要があることを学んだ。
その為には、園児が《何が好きなのか》《何に興味を持っているのか》を常に見ておくことが必要であると感じた。
保育に生かす記録という点では「子どもの育ちを見る」「自らの保育の在り方を振り返る」という2つの視点から記載するように心がけたい。
日々の保育において、自分の子どもへの関わり方は適切であったか、環境は適切であったか、“ねらい”や“内容”は適切であったかなど、振り返りをしていきたいと思った。
高島おひさまこども園 塩見 ゆりあ 記