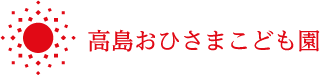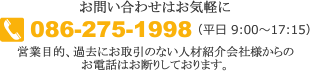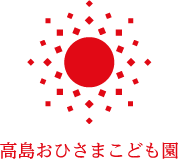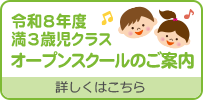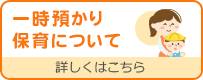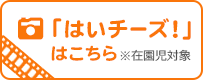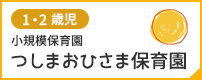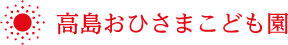NPO法人ブイ・フィットライフさん主催の『バルーン実技&運動遊び』研修に参加しました。
《バルーン》
実際にバルーンを行いながら、特性や基本姿勢、細かな指導法、起こりうるミスの防ぎ方、綺麗に見える作り方などを教えていただいた。
自分で体験することで、難しい部分も理解しやすく、様々なケースを考慮した上での指導法を聴くことができたので、実践しやすいと感じた。
また、振り付きの曲でも体験ができたのでイメージし易かった。
《運動あそび》
鬼ごっこやジャンケンなど、普段からしている遊びに少しずつアレンジを加えたゲームが多く、自分自身も十分楽しめたので、子どもたちでも理解しやすく盛り上がることができると感じた。
子ども同士でも、保護者の方と一緒に行っても楽しいゲームなので参観日などでぜひやってみたいと思った。
ゲームの内容でけではなく、スムーズに行えるようにマットを敷くなどの環境構成や指導法もあわせて教えていただき、大変有意義な研修に参加できた。
高島おひさまこども園 岡田 記