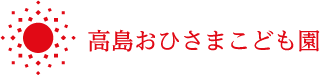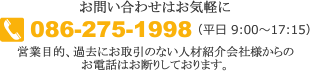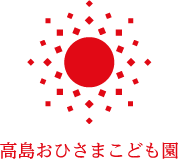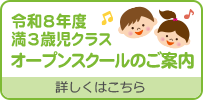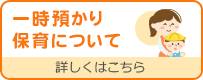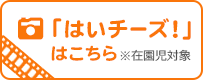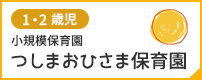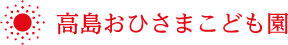岡山大学教育学研究科 准教授 横松友義先生の『幼児教育の重要性』についての研修に参加しました。
人格完成に至るまでにはプロセスがあり、一人ひとりの能力を高めていくための基礎を、0~5歳の間に身に付けていく意識をもつことの大切さを学びました。
今後は乳幼児教育の3つの根本とされている、
『自分が大切にされていると子どもが実感できている』
『自分のペースで自分のままで良いと子どもが実感できている』
『自分が行いたいことに子どもが没頭できている』
以上のことを、今後もより意識をして良い保育ができるように努めていきたいと思います。
高島おひさまこども園 宮田 記