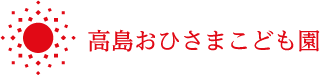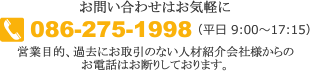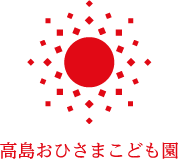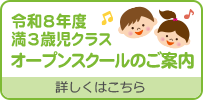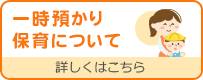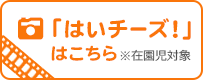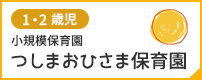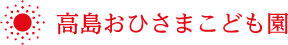キャリアアップ研修において「マネジメント」を受講しました。
『風通しの良い風土づくり』が、子どもの人権を守ることや職員が働きやすい環境にも繋がり、保育や園の質にとって重要であることを学びました。
研修を受講して、自園では効果的なサーバントリーダー体制が整っていることを感じ、感謝の気持ちとともに、その中で成長していきたいと思う気持ちが大きくなりました。
「感謝している」「頼りにしている」「助かっている」「期待している」「安心している」等、他者貢献を積極的に伝え合えたり、意見やアイデア・思い付き等が気軽に言える空気感・雰囲気づくりに努めたいです。
高島おひさまこども園 木戸美江 記