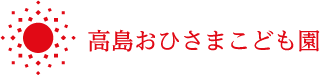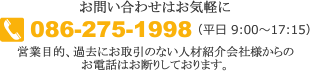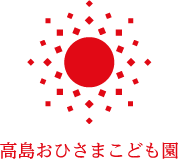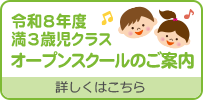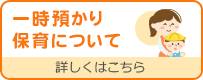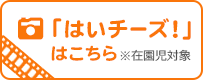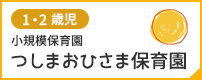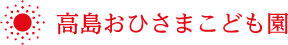キャリアアップ研修において「幼児教育」を受講しました。
幼児教育では、子どもたちが主体的に参加し協同的に学ぶ経験を積み重ねていくことで、子どもの資質や能力が育まれていくということを学びました。
保育者は子どもの遊びや生活をよく観察し、子どもが主体的に参加して深い学びへと繋がるような環境を工夫することが重要であると分かりました。
子どもたちと一緒に遊び子どもたちの世界に入れてもらうこと、子どもたちの声をよく聴くことなどを通して子どもの理解に努めたいと思いました。その中で子どもの興味や関心や困っていることなどを捉え、保育に生かしていきたいと思います。
高島おひさまこども園 右近尚己 記