今日は令和5年度入園式がありました。
可愛い1歳児クラスいちご組さん7名と、2歳児クラスみかん組さん2名を迎え、新年度がスタートしました。これから先生やお友だちとたくさん遊ぼうね!

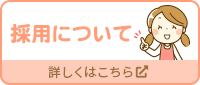

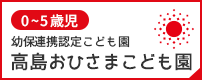
今日は令和5年度入園式がありました。
可愛い1歳児クラスいちご組さん7名と、2歳児クラスみかん組さん2名を迎え、新年度がスタートしました。これから先生やお友だちとたくさん遊ぼうね!

乳児保育についてのキャリアアップ研修を受講しました。普段子供達と接していく中で、どのように関わってあげたらいいのか等を改めて考え直すよい機会になりました。子供の主体性を尊重することが大切であることを学んだので、その点を意識しながら保育をしていきたいと思います。
谷本
障害児保育についてのキャリアアップ研修を受講しました。
具体例を通して、医療的ケアの体制についてや知的障がいのある子どもの適切な対応の仕方や見方、支援について学びました。子どもの現在の姿を的確に捉えらえ、適切な対応が出来るように心がけていきたいと思います。ご家庭や関係機関との連携をしっかりしていきたいと思いました。
佐々木
乳児保育についてのキャリアアップ研修を受講しました。
乳児保育の意義について学びました。保育士の専門性を改めて学ぶことで、乳児保育の現状と課題について考えることが出来ました。子どもひとりひとりの発達状況や姿をしっかり見て向き合い、子どもの主体性を促進する保育を心がけていきたいと思います。
佐々木
つしま幼稚園の片平園長よりチーム保育についての研修がありました。今回はつしまおひさま保育園の職員4名でグループワークを行い、「保育の中で困っている・悩んでいること」「保育の中で一番大切にしていること」「自分の得意なこと」など、様々な質問に対して自分の思いを話したり、他の先生の思いを聞いたりしました。

他の先生の思いを知ることが出来たり自分の中での気づきや反省点を考えることが出来たりしました。コミュニケーションを大切にし、先生みんなでよりよい保育をしていきたいです。
山口
虐待のニュースをふまえて、つしまおひさま保育園鳴坂先生より研修を行いました。
1日の流れの中で、子どもに対する「良くない」と考える関わりから自分の保育を見つめなおし、より良い関わりのポイントを学びました。
子どもにもっとも良いことは何かを第一に考え関わっていきたいと思いました。
森
12月15日に玉川大学大学院名誉教授 佐藤久美子先生による英語研修を受講しました。
今回は1月から3月までのカリキュラムの内容や進め方を教えて頂きました。色や果物を英語で言ってみたり、英語でのあいさつや表現の仕方など、今まで行ってきたレッスンを踏まえて、より深い内容に触れていきます。
みかん組の子どもたちはHow are you?と聞くと自分の気持ちや状態を自分で考え、英語で答えることが出来るようになっています。普段の遊びの中でも英語が聞かれていることをお話しすると「すばらしいですね!」とお褒めの言葉を頂きました。これからも子どもたちと英語の時間を楽しんでいきたいです。


10月24日に行われた玉川大学大学院名誉教授 佐藤久美子先生による英語研修を受講しました。
つしま幼稚園あんず組(2歳児クラス)の先生方とクラスの様子を発表し合う中で、普段の遊びの中でも英語に触れていると伺い、刺激を受けました。
英語の時間に楽しんだ内容を遊びの中にさりげなく取り入れることによって言葉の意味や使う状況など、より理解が深まると感じました。
今回の研修では子ども達が大好きなクリスマスの内容もあったので季節の行事に触れながら楽しく英語を取り入れていきたいです。
安藤
全国幼児教育研究協会顧問 岡上直子前税先生の研修「幼児の学びを豊かにする環境の構成~みなさんの保育記録からの学び~」に参加しました。

幼児期の各年齢の特性と保育の大切にしたいことを教えていただきました。好きな物を集める、作るなどして、それらを使い、遊ぶ楽しさを味わえるように環境を作る大切さを感じました。作ったものを使って、ごっこ遊びに広がり遊ぶ中で”こうしてみたい”と子どもから新たな発想が生まれ、保育者や友だちと考えたり作ったりして遊びが発展していきます。
1・2歳でも、遊びが発展していく楽しさを味わうことができるように興味のある遊び、扱いやすい素材の物を準備したり安全で集中して遊べる環境を作ったりしていきたいと思います。
山口
7月28日に行われた玉川大学大学院名誉教授 佐藤久美子先生による英語研修を受講しました。
研修では職員同士が英語で簡単なやり取りをし、挨拶の練習をしました。
基本の六動作(立つ、座る、回る、歩く、止まる、跳ぶ)を子ども達が身に付けるには保育者が何度もやって見せたり歌や踊りに合わせて一緒に楽しみながら行うことが大切だと教えて頂きました。
2歳児がはじめて触れる英語を楽しく導入するためには、保育者がイラストやDVDを見せながら視覚的に援助することや、なにより子どもが英語を話せたときにしっかり褒めて自信に繋げていくことが大切だと感じました。
9月から始まる英語の時間に向けて、子ども達が興味を持てるように教材など準備していきたいです。
安藤
